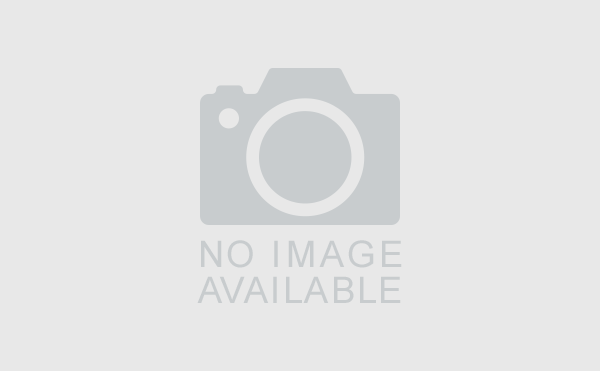第26回ウィンターカンファレンス2010(旭川)
第26回ウィンターカンファレンス2010 in Asahikawaのご案内
大会委員長
北海道大学文学研究科
和田博美
会員の皆様、2010年ウインターカンファレンス旭川についてご案内いたします。 旭川には皆様ご存知の旭山動物園を初め、北海道最高峰大雪山旭岳スキー場もあります。 圧雪車も入れない林間コースで、パウダー・スノーを満喫できます。 ふもとではクロスカントリー・スキーやスノー・シューも楽しめます。 スキーの後は、源泉掛け流しの温泉が疲れを癒してくれることでしょう。 また旭川ラーメンやジンギスカン料理などの名物も、皆様を満足させてくれることと思います。
大勢の方の参加をお待ちしています(目標60人)。参加者数によっては、格安料金の送迎バスを用意します。
大会概要
日時: 2010年3月16日(火)~18日(木)(2泊3日)
場所: 層雲峡温泉 朝暘リゾートホテル
・源泉掛け流しの温泉。サウナ、露天風呂、岩盤浴、エステを楽しめます。
・食事は和・洋・中、40品目以上のバイキング。
・旭川駅よりバスで2時間弱
・住所: 〒078-1701 北海道上川郡上川町層雲峡温泉
・電話: 01658-5-3911
・詳細はホテルホームページをご参照ください。
アクセス
◎ホテルの無料送迎バスを利用する場合
11:30発(札幌駅北口)-> 14:30(旭川駅エスタ前)->15:00(旭山動物園)->16:30着(朝陽リゾートホテル)
10:05発(朝陽リゾートホテル)->11:30(旭山動物園)->12:00(旭川駅エスタ前)->15:00着(札幌駅北口)
注1) 利用希望の方は申込書にご記入下さい。
注2) ホテル運行のバスのため他のお客様も混乗となります。満席の場合はご利用になれません。
注3) 旭川空港-旭川駅は,路線バスの利用になります。所要35分,料金¥570。時刻表は旭川空港ターミナルのホーム・ぺージをご覧下さい。
◎公共交通機関を利用する場合
道北バス、層雲峡・上川線があります(HPはこちら)。
旭川駅発: 9:15、 10:45、12:15、14:35、15:45、16:35、18:40
上川駅発: 10:35、12:05、13:35、15:00、15:55、17:05、17:55、20:00
層雲峡着: 11:05、12:35、14:05、15:30、16:25、17:35、18:25、20:30
注1) 片道料金¥1,950です。旭川駅から上川駅までJR石北本線を利用し,上記バスに乗り換える方法もあります。特急で45分です。
注2) 層雲峡からホテルまで,徒歩5~10分です。朝陽リゾートホテルに電話すれば,送迎があります。
プログラム
3月16日(火)
17:30-18:50 夕食バイキング(~21:00)
19:00-19:10 会長挨拶 磯 博行(兵庫医療大学)
19:10-20:10 教育講演
桜美林大学老年学研究科 教授 長田 久雄 先生
「学際的老年学の教育・研究を通して考えたこと」
大学院で学際的老年学の教育に携わって10年近くが経過した。この間,心理学以外を背景とする学生とともに学び研究する多くの機会を得たが,その中で「疑問」の重要性をあらためて実感するに至った。学び研究する際,意義や目的が大切であることはいうまでもないが,その裏側にある「疑問設定」のもつ意味の重大さに遅まきながら気づかされた次第である。省みれば,疑問は未知,そして未知は無知に通じるように感じ,これまでは,なかなか本音で疑問を語ることができなかったように思う。このような機会を与えて頂いたので,現時点で感じている「素朴な疑問」のいくつかを述べさせて頂くこととしたい。
20:30-23:00 若手研究者シンポジウム
企画者: 和田 博美
大学院重点化等により、研究者をめざす大学院生の数は以前では考えられないほど増加しています。 しかし院生数の増加に対して、大学教員や研究者のポスト数は増えていません。院生にとって厳しい状況にあります。 そこで若手研究者の支援と学会の活性化のために、このシンポジウムを企画しました。 発表内容は、査読を受けたのち機関誌『行動科学』に掲載される予定です。
- 周産期の甲状腺ホルモン阻害ラットにおける衝動的選択の検討
米崎 久美子・和田 博美(北海道大学)
衝動性には、ある一定の間反応を抑制することができない衝動的行動と、遅れてくる大きな報酬よりも、目先の小さな報酬を好むといった衝動的選択の2つがある。そこで、衝動的選択の視点から、甲状腺ホルモン阻害ラットに衝動性が見られるかを検討した。本実験では、2つのレバーを用い、一方のレバーには、報酬量が大きいが遅延時間が長い強化スケジュールを、他方のレバーには、報酬量は少ないが遅延時間も短い強化スケジュールを対応させた。大きな報酬を待てずに小さな報酬を選んでしまう行動応答を衝動的選択として定量化し、周産期の甲状腺ホルモン阻害と衝動性との関連を検証した。 - 事象関連電位P3成分における動物モデルの構築―ラット前部帯状皮質に着目して―
服部 稔(広島大学大学院総合科学研究科)
事象関連電位P3成分は注意を向けている刺激に対して惹起される一過性の脳電位であり,注意資源と認知過程の指標として多く用いられている。その特徴から臨床応用も期待されている成分である。しかしP3成分の神経基盤はいまだ明らかではない。近年ヒトP3成分のモデルとして動物モデルが着目されている。特にラットではヒトのP3成分に出現条件や波形の様相が近い,P3-like成分が惹起されることが知られている。本研究ではラットP3-like成分の妥当性を検討し,ヒトP3成分の動物モデルとして有用であるか検討した。適切な動物モデルを構築することで,ヒトP3成分の神経基盤を検討することが可能であると考えられる。 - 主観的疲労感と起床時コルチゾール反応との関連性
岡村 尚昌1・津田 彰2・浦田 英範3・上田 幸彦4
(1久留米大学医学部高次脳疾患研究所、2久留米大学文学部心理学科、3志學館大学大学院心理臨床学研究科、4沖縄国際大学人間福祉学科)
近年、起床後30分~60分にコルチゾールが上昇する起床時コルチゾール反応(CAR)がストレス状態を反映する鋭敏な指標として注目されている。CARは労働時間が長く、仕事の悩みが多い個人ほど著しく高いこと、休日よりも平日で高いことが明らかにされている。しかしながら、主観的疲労感がCARに与える影響についての検討は少ない。そこで、女性大学職員78名対・ロに、平日と休日のCARと主観的疲労感との関連性を検討した。その結果、疲労感の強い個人はそうでない人と比較して、平日と休日のCARが顕著であった。疲労感の強い個人は、休日でもリラックスできてない状態であること、その結果として、休日のCARも平日と同レベルで高値であることが示唆される。 - 応用行動分析にもとづく主任保育士対象の研修プログラムの効果検討
田中 善大・三田村 仰・野田 航・馬場 ちはる・嶋崎 恒雄・松見 淳子 (関西学院大学)
本研究は、主任保育士を対象に応用行動分析にもとづく発達障害児への支援に関する研修プログラムを実施、その効果を検討したものである。研修プログラムの内容は、問題の同定、行動観察、機能的アセスメント、支援の立案と実施であり、全4回から構成されていた。参加者は、1名の園児を事例として取り上げ、事例対象園児について行動観察を行い、支援の立案及びその実施を行った。研修プログラムの評価のために、研修の前後で、共通事例の支援方法について質問紙を実施した結果、支援方法の増加が見られた。また、対象園児に対する支援方法と支援後の園児の行動の変化についての質問紙調査から、支援方法の増加と、行動の望ましい変化が見られた。これらの結果から、本研究で実施した研修プログラムが効果的なものであることがわかった。 - ヒトの随伴性学習における復元効果の実験的検討
沼田 恵太郎1・嶋崎 恒雄2 (1関西学院大学大学院文学研究科、2関西学院大学文学部)
本研究では、ヒトの随伴性学習事態において、復元効果がみられるか否か検討を行った。具体的には、「新薬の服用が副作用を引き起こすか否かを観察する」というカバーストーリーに基づいたビデオゲームを作成し、薬を服用した際に患者が副作用で苦しむ可能性を1試行毎に評定させた。実験1では、新薬と副作用の対提示によって副作用の予測が増加すること、および新薬の単独提示によって副作用の予測が減弱することを示した。実験2では、架空の病院(文脈A)で新薬と副作用を対提示した後に、別の病院(文脈B)で新薬を単独提示した。その後にテストを行った結果、実験参加者は文脈A(獲得文脈)では新薬の服用から副作用を予測したが、文脈B(消去文脈)・文脈C(新奇文脈)では副作用を予測しなかった。これらの事実は、ABA復元効果がみられたこと、およびABC復元効果がみられなかったことを示している。
3月17日(火)
07:00-09:00 朝食バイキング
09:30-16:00 フリー・ディスカッション
16:30-17:30 運営委員会(宿泊室またはロビーの予定)
17:30- 夕食バイキング(~21:00)
19:00-20:00 教育講演
同志社大学 名誉教授 岡市広成 先生
「海馬の行動学的機能研究の変遷と進歩」
20世紀前半、Lashleyは労多き研究にもかかわらず、記憶に関わる脳部位を発見できなかった。世紀の中ごろ、側頭葉内側部の損傷手術を受けたH.M.の症例報告(1957)は、海馬が記憶に関係することを示唆し、海馬に焦点を当てた動物実験をもたらす引き金となった。その後20年間に多くの実験が報告されたが、海馬が記憶に関係するという一致した結果は得られなかった。このような状況の下でO'Keefe & Nadelによって提案されたのが"The hippocampus as a cognitive map"(1978)である。論者は、1974年に、この仮説の確立に向けての共同研究の最前線であったBlackの下に留学し、初めての生理心理学実験を開始する幸運を得た。それ以降35年にわたる論者の研究を中心に海馬研究の変遷と進歩を語る。
20:15-20:45 総会
20:30-24:00 シニア研究者シンポジウム
企画者: 漆原 宏次(北海道医療大学)
「現代の食行動の諸相―食の問題と行動科学的アプローチ―」
食行動は,全ての動物と同様,我々ヒトにとって,生存に直結する根源的な行動である.しかし同時に,我々の食行動は,味覚や嗜好,文化や経済,体型や健康状態の変化など,非常に多彩な要因によって影響を受ける点で特徴的である.この特徴は,裏を返せば,食行動にまつわる問題が,様々な要因の複合から生じる,複雑で解決が難しいものとなりうることを意味している.たとえば,過食や栄養の過剰摂取は,肥満や,近年定着した言葉であるメタボリックシンドロームに直結する行動であり,古くから問題視されているが,周知の通り,未だに解決には至っていない.解決が難しい背景には,この問題に,個人の嗜好,性格,行動傾向,文化的経済的環境など,様々な要因が複雑に絡み合い影響を及ぼしている事実がある.本シンポジウムでは,このように複雑かつ根源的な食行動について,行動科学的視点から問題を整理し,それに対するアプローチについて考察する。
- 食行動と生活習慣改善:過食性肥満に焦点をあてて
今田純雄 (広島修道大学人文学部 教授)
食行動は,生物的基礎をもつ学習行動であり,社会・文化の影響をつよく受ける社会行動,文化行動でもある。今回は,摂食量をコントロールする心理的要因に注目し,感性満腹感,過食の境界モデル,mindless eating,the volumetrics eating plan,感情と食行動に関するa five way modelについて概観し,生活習慣改善に対する心理学の貢献・寄与の可能性について論じていく。 - 食行動に影響する外的刺激および社会的刺激の効果
青山謙二郎(同志社大学心理学部 教授)
食行動は、どのような状況で食べるか(例えばテレビを見ながら食べるのか)、誰と食べるか(例えば少食の人と一緒に食べるのか)といった外的刺激や社会的刺激の影響を受ける。今回のシンポジウムでは、これらの要因が摂食量や食物への渇望(food craving)に及ぼす影響について、人間だけでなく動物を対象とする実験例を紹介し、健康な食生活の実現のための方策について考察する。 - ベックダイエットプログラムの紹介とその効果について
富家直明(北海道医療大学心理科学部 准教授)
メタボリックシンドローム対策が我が国の保健医療における重大な課題になっている。これまでは、カロリーの制限と運動によるダイエット方法が主流であったが、「わかっているけれどもそれができない」という理由によって、脱落者も多かった。そこで、昨年より注目されはじめている認知行動療法家ジュディスベックの心理療法をベースとしたダイエットプログラムを紹介するとともに、その実践例の紹介ならびに介入効果について報告したい。
参加申し込み
宿泊代: 1泊2食付・和室4~5名利用¥8,400です。こちらで部屋割りをします。
注1) 3名以下やグループで1室を利用したい方は,参加申込書にその旨を明記して下さい。料金は3名利用1人¥9,520、2名利用1人¥10,500です。
注2) 宿泊日の7日前以降,キャンセル料が発生します。
参加費: 学生¥2,000、それ以外¥5,000です。
申込み: 大会に参加される方は,参加申込書をダウンロードし,必要事項を記入してメールまたは郵送で申し込んで下さい。
締め切り: 2010年2月25日(木)必着
E-mail:wada@let.hokudai.ac.jp
郵 送:〒060‐0810 札幌市北区北10西7 北海道大学文学研究科 和田博美
参加申込書ダウンロード
申込書ダウンロード(Microsoft Word)
大会申し込みは締め切りました(2010年3月3日)
イベント
◎旭山動物園
ご存知ペンギンの散歩(11:00~),まっしろに変身した北極ギツネ,ユキヒョウなど,冬の動物たちが待っています。開園時間10:30~15:30,入園料¥800(中学生以下無料)。詳細は旭山動物園のホームページをご覧ください。
注1) アクセスは,ホテルの無料送迎バス(満席に注意)か公共交通機関をご利用下さい。
注2) 公共交通機関の場合,片道料金¥2,310~1,610。時刻表等の詳細はこちら。
◎スキー
・大雪山・黒岳スキー場: 大雪山の景観と良質の雪で定評のあるスキー場。上部のリフト下は初・中級者向けスラローム・コース,下部のロープ・ウェイ下は狭くて急な上級者向けダウンヒル・コースです。下部のコースは山岳スキー場のため,入山する前に雪崩情報に注意して下さい。途中に連絡小屋はありません。自力下山して下さい。不安な方はロープ・ウェイで下山して下さい。詳細はこちら。ゲレンデの動画もご覧になれます。レンタル・スキー3点セット1日¥3,000,スノー・ボードOKです。
・カムイリンクス・スキー場: 旭川駅からバスで40分。リゾート型のスキー場です。家族連れでも安心して楽しめます。詳細はこちら。
◎層雲峡氷瀑祭り
層雲峡を流れる石狩川の渓谷沿いに,巨大な氷のオブジェがそそり立ちます。昼間は太陽の光に輝き,夜間は七色の光にライトアップされ,幻想的な造形美を堪能できます。詳細はこちら。
格安バスツアーのご案内
バスツアーについて、多くの皆様から旭山動物園の希望がありました。
そこで貸し切りバス(45人乗り)を手配しましたので、ご利用下さいますようお願い申し上げます。
旭山動物園の入園料は800円(中学生以下無料)です。25名以上なら700円です。現在まで23名の希望者がおります。まだ大会参加を受け付けています。お待ちしています!
日時: 3月17日(大会2日目)
往路: ホテル発(09:00)→旭山動物園着(10:30)→旭川駅着(11:10)→カムイスキーリンクス着(12:00)
復路: カムイスキーリンクス発(14:00)→旭川駅発(14:45)→旭山動物園発(15:15)→ホテル着(16:30)
料金: 往復1,000円(一律)
注1) 皆さんの参加あっての格安料金です。ご協力お願いします。
注2) 旭山動物園のペンギンの散歩(11:00)に間に合います。
注3) ホテルの送迎バスは団体利用が難しいため、格安ツアーバスをご利用下さい。またペンギンの散歩に間に合いません(11:30着)。