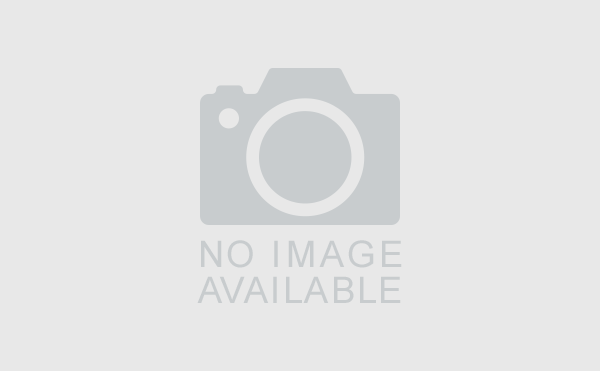第23回2015年度年次大会
2015年 第23回 日本行動科学学会年次大会のご案内
大会長 川合 伸幸(名古屋大学)
今年度の年次大会は名古屋大学(名古屋市千種区)で開催させていただきます。例年と異なり、日本心理学会最終日の翌日(9月25日、金曜日)の開催です。 これにともない、懇親会も大会の前日、すなわち日本心理学会最終日(9月24日)の夜に開催いたします。従来は日本心理学会大会の前日から大会開催地に来ていただいておりましたが、今年は日心大会の最終日にもう一泊していただくという新しい試みです。これは、日本心理学会大会の前日に会員集会が行われており、日本行動科学学会会員のみなさんが集まるのが困難になってきたこと、来年度の日本心理学会はICP2016のプログラムの1つとして開催されることを受けての試みです。プログラムは午前中だけの小規模なものですが、ぜひ日心大会後も、もう一泊していただいて、ご参加いただきますようお願いします。
拡大運営委員会は、プログラム終了後の12:00から1時間程度の予定で開催します。
【日時】2015年9月25日(金) 10:00-12:00
【場所】名古屋大学 東山キャンパス 情報科学研究科棟1F 第一講義室
【名古屋大学へのアクセス】
地下鉄名城線名古屋大学駅下車、徒歩約7分です(http://www.nagoya-u.ac.jp/access/index.html)
キャンパスマップ(A4 セクション)は、こちらをご参照ください。
pdf版のキャンパスマップはこちらをご参照ください。
【テーマ】食行動への行動科学的アプローチ
【企画者】川合 伸幸
【参加費】学会員(1000円)/非会員(1500円)
【参加証明書】 本大会に参加された方には、大会の参加証明書を発行します。本会は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会における教育研修機会(ポイント取得)としての承認学術団体です・B
【懇親会】
下記にて2015年 第23回 日本行動科学学会年次大会の懇親会開催を予定しております。
日時:9月24日(木) 夕方
場所:名古屋コーチンとMODERN和食 互坐
地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩3分 もしくは 地下鉄東山線 栄駅 徒歩6分
http://r.gnavi.co.jp/n002501/
集合場所:名古屋国際会議場 1F 日心大会受付・総合案内前
集合時間:17:45(厳守)
現時点で座席に若干名の余裕があります。新たに参加ご希望の方は9月21日までに jabs2015[at]cog.human.nagoya-u.ac.jp ([at]->@)までご連絡ください。
【プログラム】
1. 教育講演(10:05-10:50)
大矢幸弘(国立成育医療研究センター)
『乳幼児の摂食障害および条件づけされた食物アレルギーに対する行動科学的アプローチ』
最近、増えている乳幼児の摂食障害(Anorexiaではない)や食物アレルギーの減感作療法の失敗に伴う心理的アレルギーの増加について行動科学的介入が有効である。その背景にある理論や実践について、医療行動科学の観点から解説を行う。
2. シンポジウム「孤食/共食を考える」(10:55-12:00)
山中祥子(池坊短期大学)
『おいしさから食行動を考える』
これまでの研究により、「孤食」では摂食量の減少や摂食する食物の偏りの他、おいしさを感じられないなどの問題点が指摘されており、逆に「共食」のメリットとしては、おいしさや食事の満足感の上昇や、摂食量の増加などがあげられている。このことから「おいしさ」が共食・孤食を考える上で重要なキーワードであると考えられるが、実際、共食か孤食かで摂食量やおいしさの評価はどのように変化するのだろうか。
今回は、共食・孤食に関する研究を紹介し、先行研究とは異なる視点から共・H・孤食について考えてみたい。さらに「おいしさ」以外に、摂食量や摂取頻度に影響する要因として・EAあらたに潜在指標を用いた研究を紹介する。
中田龍三郎(名古屋大学)
『共食の社会的意義を探る -鏡で自分を見ると一人で食べてもおいしく感じる?』
一人での食事は味気なく、家族や仲間との食事はおいしく感じたことはないだろうか。認知レベルでの「おいしさ」は食べる環境の影響を受ける。他者が存在するかどうかはその好例であり、同じ食品を食べたとしても、一人で食事する(孤食)よりも他者と食を共にする(共食)ほうがおいしさは増す。
本発表では鏡を見ながら食事するという一風変わった発表者らの研究を先行研究とともに紹介し、なぜ共食するとおいしく感じるのか考察する。さらに高齢者のデータも紹介し、急速に高齢化が進む日本で社会問題化している高齢者の孤食を改善し、共食を促進することの重要性について解説する。
【連絡先:大会事務局】
名古屋大学 情報科学研究科 認知情報論講座 (川合研究室)
住所:〒464-8601 名古屋市千種区不老町
名古屋大学情報科学研究科 川合研究室
TEL:052-789-5179(直通)/FAX:052-789-4712
大会用メールアドレス: jabs2015@cog.human.nagoya-u.ac.jp