
 |
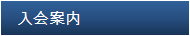 |
 |
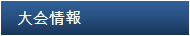 |
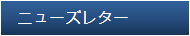 |
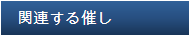 |
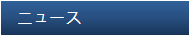 |
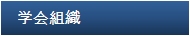 |
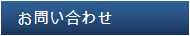 |
 |
�� ���{�s���Ȋw�w��j���[�Y���^�[�o�b�N�i���o�[
2014�N�x�@No.1�@�i2014�N5��15�����s�j
contents
1. �d�v�Ȃ��m�点�F�j���[�Y���^�[�̃��[�����O���X�g���ɂ���2. ��22����{�s���Ȋw�w��N�����̂��ē�
3. ��30��E�B���^�[�J���t�@�����Xin Kagawa�̂���
4. 2013�N�x�����
5. ���̉��̂���
6. �s���Ȋw�u�b�N���b�g�V���[�Y�@���e��W�̂��m�点
7. �ҏW�ψ����̂��m�点
8. ���ψ����̂��m�点
9. �z�[���y�[�W�f�ڏ��̂��m�点
10. �����ǂ���̂��肢
11. �_�E�����[�h
1. �d�v�Ȃ��m�点�F�j���[�Y���^�[�̃��[�����O���X�g���ɂ���
�i�����ǒ��@�c���F�K�j
�O��ɂĉ���ւ̏��`�B���X���[�Y�ɂ�����d�q�ł̃j���[�Y���^�[�s�����肷�邱�Ɠ���ړI�Ƃ��Ē�Ă��ꃁ�[�����O���X�g�̍쐬���L��ψ���Ƌ��ɐi�߂邱�ƂɂȂ�܂����B���[�����O���X�g�̍쐬�ɂ����܂����A�\�ł�����N�x���ƂƂ��āA���[�����O���X�g�ł̃j���[�Y���^�[�z�M��i�߂Ă����܂��B���[���A�h���X���o�^����Ă������̊F�l�ɂ́A��{�I�Ƀ��[�����O���X�g�ł̃j���[�Y���^�[�z�M�ɐ�ւ��Ă����\��ł��B�������A���[���A�h���X���o�^����Ă��Ȃ�����[���A�h���X�������̕��A�]���̔z�M���@����]������ɑ��āÉA���}�̂̃j���[�Y���^�[��X���������܂��B���̂��ƂɊ֘A���܂��āA�w����ǂւ̃��[���A�h���X�̂��o�^���\�Ȍ��肨�肢���Ă���܂��B�����ǂɓo�^����Ă������̊F���܂̏����G��52(2)�ɓ����������܂����̂ŁA���ڒʂ��̏�A�ŐV�̏Z�����ƂƂ��ɁA�����ǂւ��o�^���������܂��悤���肢�������܂��B���[���A�h���X�����̕��́A�\�Ȍ��育�o�^�����肢�������܂��B�C�����K�v�ȕ��́A�ł��邾�����[���ɂāA����ꍇ�ɂ�FAX��X���ɂĎ����Lj��Ăɂ��A�����������B�����ǃ��[���A�h���X jabs.office[at]gmail.com ([at]->@)
2. ��22����{�s���Ȋw�w��@�N�����̂��ē�
�i���@��{�q�Y�E���s�k��w�j
���N�x�̔N�����͋��s�k��w�i���s�s�R�ȋ�j�ł����b�����Ē����܂��B�{�w�ł�2012�N�S���ɗ��w�Ö@�w�ȂƐS���w�Ȃ���Ȃ錒�N�Ȋw�����ݒu����A�u������Ƃ��炾�̌��N�ƗՏ��v�Ɋւ��鋳��E�������n�܂�܂����B���H�R�̘[�ɂ���V�����w�ɁA�D�S�قŊF�l�����҂����Ă��܂��B�{���ł́A����ʍu���A���ҍu���ɉ����܂��āA��茤���҂ɂ��V���|�W�E������悢�����܂����B���\�҂̐搶���ɂ́A�����̗̈�ɂ�����Ő�[�̌������\���s���Ă��������܂��B��b��������Տ������܂ŁA������ΏۂƂ�����������q�g��Ώۂɂ��������܂ŁA���L���s���Ȋw�������W�J����邱�Ƃł��傤�B�܂��A�{�w����L�̌��������������c�_�������Ɍ��킳��A�����ғ��u�̌𗬂��[�܂邱�Ƃ����҂��Ă���܂��B�F�l�A�����Ă��Q���������܂��悤�A��낵�����肢�\���グ�܂��B�y�����z�@2014�N9��9���i�j13:00�`18:00
�y�ꏊ�z�@���s�k��w�D�S��E201����
�y�e�[�}�z�@�s���Ȋw�����̍Ő�[�F��b����Տ��A�q�g���瓮���܂ŁA���L���s���Ȋw������W�J����
�y���ҁz�@��{�q�Y�A��k���q�A�c���F�K�i���s�k��w�j
�y�v���O�����z
����ʍu���F�Óc���搶�i�v���đ�w�j�i���N�S���w�j
���ҍu���F�J���ʐ搶�i�����w�j�i�����S���w�j
���V���|�W�E��
�@�P�j���b��搶�i���u�Б�w�j�i�����S���w�j
�@�Q�j�����F���搶�i�Ɨ��s���@�l�Y�ƋZ�p�����������j�i����S���w�j
�@�R�j���얾�m�搶�i���s�k��w�j�i���N�S���w�j
�@�S�j�吙�h���搶�i���s�k��w�j�i���w�Ö@�w�j
�y�Q����z�@�w����i1000�~�j�^��w����i1500�~�j
�y���e��z
�@���I����A�R�ȉw�O�ɂč��e���\�肵�Ă��܂��B�����ғ��u�̌𗬂�������̏�ƂȂ�܂��悤�A�����̂��Q�������҂����Ă��܂��B
�y���Q���\�����݁z
�@2014�N8��31���i���j�܂łɁA�Q���Җ��A�������A���e��Q���̗L�������L�̑����ǂ܂ŁAe-mail�ɂĂ��m�点���������B
�y�A����F�����ǁz
�@���s�k��w���N�Ȋw�� �S���w�ȁi��{�������j
�@��607-8175�@���s�s�R�ȋ���R�c��34
�@TEL 075-574-4307(����)�^Fax 075-574-4122
�@���p�A�h���X�Fjabs-taikai[at]tachibana-u.ac.jp�i[at]->@�j
3. ��30��E�B���^�[�J���t�@�����Xin Kagawa�̂���
�i���@��� �S���E�l���w�@��w�j
3��19��(��)��20��(��)��2���Ԃɓn��܂��āA��30��E�B���^�[�J���t�@�����X�����쌧�Օ����́u���ƂЂ牷��@�ՎQ�t�v�ŊJ�Â���܂����B�ȉ��ɁA���̏��ɂ��ĊȌ��ɂ������Ă��������܂��B����̍u���́A��N���l�ɓ��ʍu��2��Ƌ���u���y�я��ҍu�����e�P�肸�̌v4������肢���܂����B�J�Òn�̍��쌧�ɂ䂩��̂�����X��A���l�Ɖ��̂�����X�����Ăђv���܂����B�܂��A��茤���҂ɂ��V���|�W�E���ɂ́A5���̕��X�ɘb������Ă��������܂����B�ŏI�I�ɂ́A�\�肵�����\�Ҙg�ȏ�ɐ\�����݂�����A���Ԙg�̓s����A���\��t�����f�肳���Ă������������������A���Ƃ��Ă͊������ߖ�������悤�ȏł����B�����A���f�肵�����ɑ��Ă͔��ɐ\����Ȃ��v���ł���܂����B�����́A�܂��͎v�t���₹�ǂɑ���Ƒ��Ö@�����ʃe�[�}�Ƃ��āA�ΐ쌳�搶�i�����w�j�Ɠ��L�搶�i���J��w�j�̂���l�ɂ��u�������Ă����������B����l�Ƃ��A���{�ł͂��̗Ö@�̑������I���݂̕��X�ł���A���̌o���܂���ꂽ���杓I�ȓ��e�̂��b�ł���܂����B10�N�X�p�[���ŗÖ@�̂�������������ω����Ă������Ƃ��M���܁E����B�c�O�ł������̂́A�ΐ�搶������������Ă���DVD���f�������ł��Ȃ����ԂƂȂ�A��̓I�Ȏ��Õ��i��q�����邱�Ƃ�����Ȃ��������ł���܂����B�����㔼�̃V���|�W�E���ł́A���̑��̓����ł�����A���\���Ղ��Ă̎��^�����������ƂȂ�A�^���ȋc�_���傢�ɂȂ��ꂽ�B���������āA���Ԃ����Ȃ肸�ꍞ�݁A�S�̂̏I�����Ԃ�1���Ԉȏ���x���Ȃ�Ƃ�����ԂƂȂ�A���t���ς�鎞���߂��܂Ő���オ���Ă��܂����B2���ڂ́A�����ɂ������珬�J���ς���Ƃ����V��ƂȂ�A����҂�̐Βi��o��ɂ͖��͂���قǖ����������̂́A�{�{�Ŏ]��x�m�]����̂͊���Ȃ������悤�ł����B����ł������̕��X���Βi�o������ꂽ��A���ǂ���ɍs����A�]�ǂ�����\���ꂽ�肵���悤�ł����B�[�H��̔��\�̕��ł́A�܂��͓��ΕۍL�搶�i���É���w�j�ɋ���u���Ƃ��āA��N�ɑ����A�Z���G�̃X�g���X���_�̖��_�ɂ��Ă��u�������Ă��������܂����B�����f�[�^�v���͂������ꂽ���ʁA�X�g���X�̌����͂��ׂĐS���I�����ł���ƌ��_����Ă��܂����B�����āA����m�u�搶�i�@����w�j�ɂ́A���ҍu���Ƃ��ăt���[���_�ɂ��āA���ؓI�ȃf�[�^�������Ȃ����������Ă��������܂����B���̍u���ɑ��ẮA�Óc������߂Ƃ��đ����̕�����̎��₪�Ȃ���A�t���A�S�̂�����オ������������܂����B���̌�A�O���ɑ����Ă̎�茤���҂ɂ��V���|�W�E���Ƃ���3��̔��\���Ȃ���܂����B�����ł��A�t���A����̔������������A���ꂼ��Ɋ����ȋc�_���Ȃ���܂����B���̌��ʁA�O���̔ӂƓ��l�ɁA�S�̂̏I��������1���Ԃقlj��т��ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B2���Ƃ��A2����ł́A��N�̒ʂ�[��܂ł���ɋc�_�����킳��A�܂����ł͕����Ȃ��悤�ȓ��e�̘b�ŁA�傢�ɐ���オ����������Ă���܂����B����ɂ��Ă��A����m��Ȃ��悤�ȕ�����������ꂽ�̂ɁA���X��������܂����B�������I���Ă̍���̔��ȓ_�Ƃ��ẮA���Ԃ̐ݒ�̖�肪��������Ǝv���܂��B�����̊g��^�c�ψ���A�܂��啝�Ɏ��Ԃ����ɂ��ꍞ�݁A�[�H�̊J�n�������肬��ɂȂ������Ƃ���ɁA���̌�̃X�P�W���[��������ɒx��Ă����܂����B���Ԃ̓s����A�����[�H���ɏd�˂����Ƃ��A���Ԃ����ꍞ�ވ���ɂȂ����Ǝv���܂��B���̓��́A�h������Ȃ��Q���҂�2������ꂽ�̂ł����A���̓��̍Ō�̔��\�O�ɋA�炴��Ȃ��ɂȂ�ꂽ�悤�ł����B�c�_�������ɂȂ�̂́A���̉�̗ǂ������ł́E���̂ł����A�\�莞�����啝�ɂ����̂́A���㌟���̕K�v������Ɗ����܂����B����ɂ́A���\�̎��ԑт�����܂ŗ[�H��Ɍ��߂Ă���܂������A���Ԃ���������̂悤�ȏ��ӂ݂�ƁA�J�n�̎��Ԃ������Ƒ��߂āA�[�H��2���ԑO�ɐݒ肷�邱�ƂȂǂ����㌟������Ă݂�̂��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B����ȍ~�A���ЂƂ����̑S�̂̎��Ԑݒ���l�����Ă���������Ǝv���܂��B�Ō�ɁA�����ł̔��\�ҋy�є��\��ڂ��A���߂Ĉȉ��ɂ��Љ�Ă����܂��B�����\�����Ă������������X�͖ܘ_�̂��ƁA���Q���������������X�S���A����ɂ͂����͂��������������̊F�l�ɐS������\���グ�܂��B�y����P���ځi3��19��)�z
���i��E�i�s�F��ؗS���i�l���w�@��w�j
���ʍu���P�@�ΐ� ���i�����w�t���a�@�j
�w�v�t���₹�ǁ\�V�X�e���_�Ƒ��Ö@�ł̗Տ��Ɠ��ǃ��f�������ł̎����x
���ʍu���Q�@���@�L�i���J��w�j
�w�Ƒ��Ö@�A���邢�̓u���[�t�Z���s�[�̍l�����ƕ��@�|�ېH��Q�̎����ʂ��ā|�x
���i��E�i�s�F����C��
�i�����s���N������ÃZ���^�[�������j
�V���|�W�E��1-1
�@���ˁ@�F�I�ށi�k�C����w��w�@�j
�w���Y���̍b��B�z�������j�Q�����b�g�̈ړ��I���ӂɋy�ڂ��e���x
�V���|�W�E��1-2
�@�����@�`�i���������P�A�N���j�b�N��X�j
�w�����_��p���Ă���D�P��]�̕s���NJ��҂ɑ���F�m�s���Ö@�̎��H�x
�y����Q���ځi3��20���j�z
���i��E�i�s�F��ؗS���i�l���w�@��w�j
����u���@���@�ۍL�i���É���w�j
�wSelye�̃X�g���X���_�͔ގ��g�̎����f�[�^�ɂ���ďؖ�����Ȃ������x
���ҍu���@���@��m�u�i�@����w�j
�w�t���[�o���\�|�W�e�B�u�Ȕ��B�ƐS���I�E�F���r�[�C���O�ւ̉\���x
���i��E�i�s�F�������g�i���M��w�j
�V���|�W�E��2-1
����C��E��t�I�I�E��������
�@�i�����s���N������ÃZ���^�[�������j
�w2011�N�����{��k�Ђɔ����}�E�X�̍s���ω��ɋy�ڂ��W�A�[�p���̌��ʁx
�V���|�W�E��2-2
�@�����@���s�i���u�Б�w��w�@�j
�w�c�����̎Љ���B�ɂ����鎋�_�擾�\�̖͂����̌����x
�V���|�W�E��2-3
�@�員�@�O�T�i�L�����ۑ�w�j
�w�ɉ�������ԕ\�ۂ̓��I�ω��̉ߒ��x
�E�B���^�[�J���t�@�����X�̗l�q
4. 2013�N�x�����
�i�����ǒ��@�c���F�K�j
2013�N�x����A���ƂЂ牷��ՎQ�t�ɂ�����2014�N3��19���ɊJ�Â���܂����B �葫���ɒB���܂���ł����̂ŁA������ƂȂ�A�R�c�����̏��F�͂��̃j���[�Y���^�[�̍��m�ɂ���čs���܂��B�ȉ��ɁA��o���ꂽ�c�ĂȂ�тɉ�����ł̐R�c�̌o�߂��f�ڂ��܂��̂ŁA���ĂɈًc�̂������́A7��31���܂łɁA�����ǂ܂Ń��[�����ł��ӌ������������܂��悤���肢�\���グ�܂��B��ɂ��A�j���[�Y���^�[���t����2�����ȓ��ɉ�������̉ߔ����������ɂ���Ĕ�����Ό��c�������ɂȂ�܂��B���ًc�����Ȃ������ꍇ�́A���F���ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��܂��B�y�����z
1) ����̈ٓ��i�����ǁj
2014�N2���������݂̉������202���i���A���_���2���j�ł���|�A�����ǂ�����ꂽ�B���̂���9�����Z���s���ƂȂ��Ă���B2012�N�x�����ȍ~�A15�����V���ɓ���A2013�N�x������������8�����މ�̗\��ł���B
2) ��v���ԕi�����ǁj
a. �����̕�����25�N�x���Ɋւ��āA����[�߂�ׂ�200�����A�[���҂�128���i�[����64.0%�j�ł������i2014�N2���������݁j�B
�����[�̉���́A�������݂ɂ����͂��肢���܂��B
�w��̔��ɂ��āA�G��51(2)��52(1)�̍w�Ǘ���1��28�����ȂđS�Ă̋@�ւ���̓����ρB52(1)���@�֍w�ǂɂ��̔��悪1�@�֑������B�G�����ɂ��ẮA�G���̕ʍ����ҕ��S���A����сA��t����ł���B
b. �x���̕�
�����ǂ̏��Օi��́A�w��������ƒ������̍w���ɂ��B�ʐM�E�^����́A���މ�Ɋւ���ʒm����ѐU���萔������ł���B�w��E�j���[�Y���^�[�֘A�X����́A����ւ̔����ƍđ����ł���B���̂����j���[�Y���^�[�֘A�X����ɁEN�x�����\�Z����̑啝�������邪�A�G���ɓ������Ĕ��������������������߂ł���B�{�w������͒c�̂ƂȂ������{�S�����C�Z���^�[�ւ̊�t���ɂ��ẮA�N�x�����\�Z�Ɍv�サ�Ă��Ȃ��������ߗ\������x�o�����B�܂��A���Êw�p�V���|�W�E���ɂĖ{�w��Ƃ��Ă̈��A�����߂�ꂽ�ۂ̉����ɂ��Ă��\�����x�o���錩���݁B
c. ���ʉ�v
���������̑��͑����Ȃ��B
2) 2013�N�x���ƕi�����ъe�ψ���j
a. �m���ψ���֘A�n2013�N�x�J�Â̔N�����i2013�N9��19���A�D�y�R���x���V�����Z���^�[�ɂĊJ�Áj�ƊJ�Ò��̃E�B���^�[�J���t�@�����X���ɂ��ĕ��ꂽ�B
b. �m�ҏW�ψ���֘A�n�G���u�s���Ȋw�v52(2)�̕ҏW�ɂ��Đ������������B52(2)��3���ɔ��s�A4�������̗\��ł���B�����ɔ�������Ă��܂��B���茳�ɓ͂��Ă��Ȃ�����̕��������܂�����A�����ǂ܂ł��A�����������B
c. �m�o�ňψ���֘A�n�u�b�N���b�g1����9�ɑ����āA10���w �b���F�b���Ƃ��ɉ����N�����Ă���̂��H�x���ˌb���q ���i2013�N11��30���o�Łj�������N�x�Ɋ��s���ꂽ���Ƃ����ꂽ�B�V���ȃu�b�N���b�g�̎��M�Ȃ�тɊ����̍w����̔��ւ̋��͂Ɋւ��āA����̊F�l�ւ̈˗����������B
d. �m�L��ψ���֘A�n���s�z�[���y�[�W�̍X�V��V�z�[���y�[�W�̍쐬�A�j���[�Y���^�[�̕ҏW�ɂ��ĕ��ꂽ�B
�y�R�c�����z
1) 2013�N�x���Z�����2014�N�x�\�Z�Ăɂ��āi�����ǁj
2013�N�x���{�s���Ȋw�w��Z�̏��ށi�܁A��v�č��j�y��2014�N�x�\�Z�Ă̓z�[���y�[�W�Ō��J�����Ă���܂��B�ȉ�URL���_�E�����[�h�̂����A���Q�Ƃ��������B������́A3�������̉�v�N�x���ߓ��܂ł̌��Z�Ƃ��̉�v�č��̌��ʂ��������Ă��������Ă���܂��B2014�N�x�\�Z�Ăɂ��Ă��A���̌��Z���Ă̌J�z���f�������̂ƂȂ��Ă��܂��B�\�Z�Ăɂ�����x�o���ɂ��܂��āA���ŕ�3%���l�����Ă��A�T�ˍ�N�x�Ɠ��l�̗\�Z�͈̔͂Ɏ��܂錩���݂ł��B�������A���⏕��ɂ��܂��ẮA�w���e���^�c�҂֗�N�Ɠ����x�̕⏕��ۏႷ�邽�߂ɗ\�Z���Ƃ��Ă��܂��B
2) 2014�N�x�̎��Ɠ��ɂ��āi��j
a. �N������уE�B���^�[�J���t�@�����X�iWC�j���ɂ���
�N�����́A��{�q�Y�N�����ψ����i���s�k��w�j�̉��ŁA���S���̑O��9��9���i�j�ɊJ�Â��邱�ƂɂȂ����i�{���u��22����{�s���Ȋw�w��N�����̂��ē��v�����Q�Ƃ��������j�BWC���ɂ��ẮA��c��WC���ψ����i�L�����ۑ�w�j�̉��ŁA2�E3�����̗\��ł���i���Ă��܂Ƃ܂�܂�����w��z�[���y�[�W��j���[�Y���^�[�ɂĈē����Ȃ���܂��j�B
b. �w����p�̃��[�����O���X�g�쐬�ɂ���
�O��ɂĒ�Ă��ꂽ���[�����O���X�g�̍쐬�i����ւ̏��`�B���X���[�Y�ɂ�����d�q�ł̃j���[�Y���^�[�s�����肷�邱�Ɠ���ړI�Ƃ��āj��i�߂邱�ƂɂȂ����B���[�����O���X�g�̍쐬�ƈێ��Ǘ��ɂ��ẮA�z�[���y�[�W�p�T�[�o�[�̊Ǘ��ϑ���ɂ��킹�Ĉ˗�����B���̂��߁A����̃��[���A�h���X�����̈ϑ���ɗa���������Ō��d�ȊǗ����˗����邱�ƂɂȂ�B
c. �j���[�Y���^�[�̃��[���z�M���ɂ���
���[�����O���X�g�̍쐬�ɂ���邪�A�\�ł�����N�x���ƂƂ��āA���[�����O���X�g�ł̃j���[�Y���^�[�z�M��i�߂�B���[���A�h���X���o�^����Ă������ɂ́A��{�I�Ƀ��[�����O���X�g�ł̃j���[�Y���^�[�z�M�ɐ�ւ���B�������A���[���A�h���X���o�^����Ă��Ȃ������[���A�h���X�������̉���A�]���̔z�M���@����]�������ɑ��ẮA���}�̂̃j���[�Y���^�[��X������B
3) ���_����̐��E�ɂ��āi�^�c�ψ���j
���5���Ɋ�Â��A���s�A���搶�i2013�N�x�܂Ő�����j�ɁA2014�N�x����{�w��̖��_����ƂȂ��Ă����������Ƃ��^�c�ψ���Ƃ��Đ��E���邱�ƂɂȂ�܂����B���s�搶�̖{�w���s���Ȋw�ɑ��邲���т͑����ł��̂ŁA��_�̂݁A1998(H.10)�N4��1������2003(H.15) �N3��31���܂Ŗ{�w��̉�����߂��������܂������Ƃ������ɋL���܂��B
4) �V�����̐��ɂ��āi�^�c�ψ���j
���6����(4)��(12)�Ɋ�Â��A�^�c�ψ���Ƃ��Ď����������̒Óc���搶�i����ځj�Ɍp�����Ă����������Ƃ����肵�܂����B������ĒÓc����A���5��(7)(8)(11)�Ɋ�Â��A�V�����̐����ȉ��̒ʂ莦����܂����B�C����2014�N4������2�N�Ԃł��B�����܂łɖ{�����̐��ւ̋^�`�̐\���o���Ȃ��ꍇ�́A���F����܂��B�܂��w��^�c�̒��f�E�����邽�߁A2014�N4��1�����珳�F�܂ł̊Ԃ����̖����Ƃ��Ă��A�C�����������Ƃɂ������Ǝv���܂��B
�y���{�s���Ȋw�w���������E2014�N4���`2016�N3���z
��F�Óc ��
�����ǒ��F�c�� �F�K
�����ǎ����F���� ����
�^�c�ψ��F
���k�C���E���k�n�恄�c�� ����A���� �G��
���֓��E�b�M�z�n�恄���� �C��A���R ���q�A���c �p�q�A��{ �e�q
�����C�n�恄���� �G��
�����n�恄���R �ɒm�Y�A��{ �q�Y
�������E�l���n�恄��c ���A��� �S��
����B�n�恄��c �K�F�A� ����
�ҏW�ψ���F��{ �q�Y���A���c �L�A�� �q���A��s �N���Y�A���� �M�v�A�Y�c �p�́A��k ���q�A���V �C���A���c�� ���A�x�� ��
���ψ���F�썇 �L�K���A���� �G���A���� ����
�o�ňψ���F��c �Ȍၦ�A���� �܂�݁A���� ���l�A���c �p�q
�L��ψ���F���� �C�ꁦ�A���� �܂ǂ��A���� ���g�A���� �����
��v��F�� ���s�A���c �v�Y
���e�ψ���̈ψ���
�y����̈ٓ��z 2013�N�x���̉���̈ٓ��͎��̂Ƃ���ł��i2014�N3���������݁j�B
1) �����15���i�h�̗��j
���� �W���^���� ���s�^�剮 ���q�^�T�� ���a�q�^�É� ���q�^�㑺 �Ɂ^���� ���m�^���� �ށX�q�^���� �`�^�� �r���Y�^���� �N�l�^���� ���^���J �z��^���c ��݁^��c �R��q
2) �މ��8���i�h�̗��j
�ؑ� �T�^�Ė� �v��^�_�� �h��^���� �`�F�^���X�� �Ɓ^�z�� �[�q�^�� �M�q�^�g�c ����
3) �Z���s����8���i�h�̗��j
�A�� �F�M�^���X �p���^���� ���^�F�� ����Y�^��� ���q�^���� ���^���R ��F�^���� �a�Y
��������̌�1���̕����炲�A�������������A��N�x���Ɠ���̕����Z���s���̂܂܂ƂȂ��Ă��܂��B����̊F���܂ŁA�Z���s��8���̕��̘A����������m�̕��������܂�����A���`�������������܂��悤���肢�������܂��B
5.���̉��̂���
�i���̉��\�@�������g�j
�y���{�w�p��c�֘A�V���|�W�E���Q���z2014�N3��7���A���{�w�p��c�ɂĊJ�Â��ꂽ�u���A�J�f�~�[�ψ����茤���҃l�b�g���[�N�������ȉ�v�A�u�V���|�W�E���F��茤���҃l�b�g���[�N���p�Ɍ����āv�A�u�w�ی𗬃|�X�^�[���\��v�ɁEA���{�s���Ȋw�w����̉��\�Ƃ��ĎQ�����܂����B���߂ɊJ�Â��ꂽ���A�J�f�~�[�ψ����茤���҃l�b�g���[�N�������ȉ�i�ȉ��A���ȉ�j�̓I�u�U�[�o�[�Ƃ��ĎQ�����܂����B���ȉ�ł́A����܂ŋc�_���d�˂Ă����̓��e�ɂ��Ă̍ŏI�m�F�A�����ߌ�ɍs�����L�V���|�W�E���ɂ��Ă̊m�F�A�����ĕ��ȉ�̍���̗\��ɂ��Ęb�������܂����B���́A���̉��\�Ƃ��ē��{�w�p��c�ŊJ�Â�����ɏo�Ȃ���悤�ɂȂ�A���@�ւ��ʂ��������ɂ��Ēm��܂����B�����m�̕���������Ǝv���܂����A���{�w�p��c�͓��t�{�̓��ʋ@�ւ̈�ŁA�����A�Ȋw�Ɋւ���R�c�A�Ȋw�҃R�~���j�e�B�[�̘A�g�A�Ȋw�Ɋւ��鍑�ی𗬁A�Љ�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ���������S���Ă��܂��B���{�w�p��c�ɂ͗l�X�ȃZ�N�V�������݂����Ă���A����A���͂��̃Z�N�V�����̈�ł��镪�ȉ�ɎQ�����܂����B�����āA���̕��ȉ�ł܂Ƃ߂�ꂽ�����́A��ɍ\�z����������茤���҃l�b�g���[�N�̌o�܂̐����A������p���I�����W�I�ɉ^�p���邽�߂̗v����v�|�Ƃ��Ă��܂����B��茤���҃l�b�g���[�N�̖����ɂ��܂��Ă͐�̃j���[�Y���^�[�ŏЉ�܂������A����̒������܂��āA����̉Ȋw����ł͓��l�b�g���[�N���ϋɓI�ɉ^�p����A��L�̒��ɂȂ�Ƃ̈�ۂ������܂����B ���ɎQ�������V���|�W�E���i��茤���҃l�b�g���[�N���p�Ɍ����āj�ł́A���ȉ�ψ����̊��r�݂䂫�搶���u���l�b�g���[�N�̌p���I�^�p�Ɗg�[�Ɍ����āv����A���ɑ吼�����{�w�p��c����u�w�p��c�̎����ւ̎��g�݁v�ɂ��Ă��b������A�Ō�ɕ����Ȋw�Ȑl�ސ���ے��̏����������u�䂪���̉Ȋw�Z�p�l�ސ���Ǝ�茤���҂̈琬�v�ɂ��Ă��b������܂����B�吼��́A����̎��A�J�f�~�[�ψ���݂̍���ɂ��Ă��b������A���ψ���́A���N�x10��1�����ψ���̖��̂��O��A�u���A�J�f�~�[�v�ƂȂ邱�Ƃ����\����܂����B����܂ł̈ψ���Ƃ̖��m�ȈႢ�͒肩�ł͂���܂��A�g�D�Ƃ��đ̌n���������̂ɂȂ�A�K�͂͂���܂ł�30��������60���ɂȂ邱�Ƃ��Љ��܂����B���A�J�f�~�[��30����45�̎�茤���҂ō\������A�\�����̔C����6�N�ԂɂȂ�Ƃ̂��Ƃł��B�����ASTAP�זE�ɒ[�����茤���҂̂�����̖��ȂǁA����͎��A�J�f�~�[�ŗl�X�ȋc�_���W�J�������̂ƍl�����܂��B�܂��A���̏������̔��\�ł́A���m�l�ނ̃L�����A�p�X�̑��l���Ɋւ��鍑�E̎{�Љ��A���̈��Ƃ��āA�ŋ߁A�e��w�Ŏ�������n�߂Ă��郊�T�[�`�E�A�h�~�j�X�g���[�^���x���̂��b�����Ƃ��ł��܂����B �Ō�ɎQ�������w�ی𗬔��\��ł́A���{�s���Ȋw�w��̊������e�ɂ��ă|�X�^�[���g���Ĕ��\���A���ɑ��l�Ȋw��̎��̉�̕��X�ƌ𗬂��邱�Ƃ��ł��܂����B���\�ɎQ�����ꂽ�c�̖��̈ꕔ�����A�J�f�~�[�ψ���̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B�܂��A�������\�Ɏg�p���ꂽ�|�X�^�[���_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA���L�����Q�Ƃ��������B
���A�J�f�~�[�ψ���z�[���y�[�W
�y���{�s����w��w�p����V���|�W�E���Q���z
2014�N3��8���A���{�s����w��w�p����ŊJ�Â��ꂽ�V���|�W�E���u�s����w�̃R�A�J���L�������̒�āv�ɃV���|�W�X�g���ĂƂ��ĎQ�����܂����B����́u2023�N���v��w�i�ɊJ�Â��ꂽ�V���|�W�E���ł��B���{���܂ށA�č��E�J�i�_�ȊO�̈�w���o�g�҂��č��ň�t���Ǝ�������ɂ́A�č���t���Ǝ����̎��i��R������Educational Commission for Foreign Medical Graduates�iECFMG�j�����A���i���Ȃ���Ȃ�܂���B��w���番��ɂ�����u2023�N���v�Ƃ́A����ECFMG���A2023�N�ȍ~�͍��ۓI�ȔF������w���o�g�҈ȊO�̐\����F�߂Ȃ��ƒʍ��������Ƃ��w���܂��B���̒ʍ���2010�N�ɍs���A������āA2011�N�ɂ͑S����w�����a�@����c�ɂ��u��w����̎��ۏ،����ψ���v���������܂����B�܂��A�����Ȋw�ȑ�w���v���i�ϑ����Ƃɂ��u���ۊ�ɑΉ�������w����F�ؐ��x�̊m���v���̑�����A������w�A�������q��ȑ�w�Ȃ�5��w���A�g���A�����x�̊m���Ɍ������������s�����Ƃ����܂��Ă��܂��B�����āA���۔F�؎葱���̒��ŁA�J���L�������̑啝�Ȍ��������s���A���̉ߒ��ōs���Ȋw�̏d�v�����N���[�Y�A�b�v����܂����B�J���L�������̑傫�Șg�g�݂ɂ��܂��Ă͎������_�E�����[�h�ł��܂��̂ŁA���Q�Ƃ�������悤���肢�v���܂��B��w���ɂ�����s���Ȋw����̏d�v�����F�������Ɏ��������݁A�J���L�������̏ڍׂɂ��čs���Ȋw�֘A���w��m�b���������A�ǎ��̃J���L�������\�z�̂��߂̃A�C�f�A���o�����Ƃ��V���|�W�E���̖ړI�ł����B������w�������Ƃ��ċΖ������������Ƃ���A����̃V���|�W�E���œ��{�s����w�w����\���Ĕ��\����悤�Óc��E��������A�Q�����܂����B �V���|�W�E���ł͍s���ϗe�e�N�j�b�N�̕W�����Ɋւ��鍑�ۓ����A�s����w�R�A�J���L�������쐬�̔w�i�A���{�ی���Ís���Ȋw��̊����A��w�����Ǝ��ɋ��߂���s���Ȋw�Ɋւ���R���s�e���V�[�A���ۍs����w��s�����e���̍s����w����Ɋւ��钲�����ʂȂǂ��Љ��܂����B���Y�V���|�W�E���ɂ����āA���́u�s����w�̃R�A�J���L��������ĂɌ�����JABS�̎��g�݂Ƌ��߂�������v�Ƃ�����Ŕ��\���܂����B���\�ł͎n�߂ɁA���{�s���Ȋw�w��iJABS�j�ɂ��Ă̊����̗��j�A����̊w�p�I�w�i�A�������e�Ȃǂ��Љ�A���ɁA�s����w�̃R�A�J���L��������ĂɌ�����JABS�̎��g�݂ɂ��ďЉ�܂����B��̓I�Ȏ��g�݂̈��Ƃ��āA������w����ɂ����čs���s���Ȋw�̍u�`���Љ�A���ɁA�w��S�̂Ƃ��čs���R�A�J���L��������ĂɌ��������g�݁i�s���Ȋw���T�o�łɌ������c�_�A�u�b�N���b�g�̏o�łȂǁj���Љ�܂����B���̍s���֘A�w��Ɣ�r�����ۂ�JABS�̑傫�ȓ����ɁA�w��̎���͈͂̍L���ƁA�s���Ȋw�̊w��̌n�ɂ��ċc�_���d�˂�p�����������܂��BJABS�͍s���̑����I�ȉȊw�̍\�z�Ƃ����ڕW����l�X�Ȑ��Ƃ��W����Ƃ��ċ@�\���Ă��܂����A����Ŋw��̌n�ɞB�����������A���̌��ʁA�s���Ȋw�Ƃ͉����ɂ��ċc�_�������j�������Ă��܂��BJABS�̂��̓����́A�s����w�̃R�A�J���L��������Ăɍۂ��āA�s����w�̗֊s������ɂ��邱�Ƃɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł���ƍl���A����\�̒��ŏЉ�܂����B�܂��A���\�̍Ō�ɁA���ꂩ��ϊv�𐋂���s����w�ɂ�����JABS�̍v���݂̍���Ȃǂɂ��Ĉӌ����q�ׁA���̍s���֘A�w��̕��X��������JABS�̖����ɂ��ċc�_��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B�����̃_�E�����[�h�͉��L�����Q�Ƃ��������B
6. �s���Ȋw�u�b�N���b�g�V���[�Y�@���e��W�̂��m�点
�i�o�ňψ���ψ����@��c�Ȍ�j
�s���Ȋw�u�b�N���b�g�V���[�Y�́A���݂܂ł�10�����o�ł���Ă��܂��B1 �w�o����F�o�������Ƃ��Ȃ��v���o���Ȃ��Ȃ�̂��낤�x���s�L��
2 �w���ށF���Ȃ��͉����ǂ̂悤�Ɉ���ł��܂����H�x�锎�s
3 �w�₹��F�얞�ƃ_�C�G�b�g�̐S���x���c���Y
4 �w���C�ɘV����F�����S���w�̗��ꂩ��x���s�m�q
5 �w���܂��F���������w���猩��َ��̐��E�x�����K�O
6 �w���߂�F�ӎv����̐S���w�x�������
7 �w�z���F�i���̍s���Ȋw�x����N�u
8 �w�H�ׂ�F�H�ׂ����Ȃ�S�̂����݁x�R����Y
9 �w�x�ށF�X�g���X�ƑΏ��@�x���ΕۍG
10 �w�b���F�b���Ƃ��ɉ����N�����Ă���̂��H�x���ˌb���q
���i��1��600�~�ł��B�������銪�̍w�������肢���܂��B�������͓�r�Ђ֒��ڂ��肢�������܂��B���͉��L�ɂ���܂��B
��r�Ѓz�[���y�[�W
���e�͏]���ʂ�̕��j�Ōp�����ĕ�W���Ă��܂����A�o�Ŕ�p�ɂ��܂��ẮA�o�ňψ���ɂ��₢���킹���������B����̊F����̗͍�̌��e���W����ƂƂ��ɁA�s���Ȋw�u�b�N���b�g�̊��p����낵�����肢�\���グ�܂��B
7. �ҏW�ψ����̂��m�点
�i�ҏW�ψ���ψ����@��{�q�Y�j
2014�N4�����A�ҏW�ψ��������������邱�ƂɂȂ�܂����B���݁A�ҏW�ψ���ł͔N�ɂQ��̊w��s���Ă��܂��B�ҏW�K��Ɋ�Â��A�N�����A�E�B���^�[�J���t�@�����X�ł̍u���E���\���e�́A�˗��_�������肢���邱�ƂɂȂ�܂��B�w����̊F���܂���̓��e�_���ɂ��܂��ẮA��b�������牞�p�����܂ŁA���L���̈悩��̓��e�����҂����Ă���܂��B�ҏW�ψ��̐搶���̂����͂̂��ƁA�v�����K�ȐR�����s���Ă��������ł��B�{�w��̖ړI�ɍ��v�����w��̍쐬�Ƃ��̏[���ɍۂ��܂��āA�w����̊F���܂̂������Ƃ����͂����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B8. ���ψ����̂��m�点
�i���ψ���ψ����@�썇�L�K�j
���N�x������ψ����߂�썇�ł��B�ǂ�����낵�����肢���܂��B�O�N�x�܂ł͊w��̊č����A���̑O�͎����ǒ��ƁEA�w��̓��e�Ƃ������^�c��Ǘ��̖ʂ���w��ɂ�������Ă���܂����B�s����Ȃ��Ƃ������̂ł����A�v���đ�w�̉��{�����搶�Ɩk�C����Ñ�w�̎����G���搶�Ƃ����A���ꂼ���b�ƗՏ��ɏڂ����搶�Ɉψ��ɉ�����Ă��������Ă���܂��̂ŁA���̂���l�̗͂āA�w������肽�Ăčs�������Ǝv���܂��B�����킢�A�O���ψ����̘a�c�����搶�����N�x�̔N�����i���s�k��w�@��{�搶�@���S���j��WC�i�L�����ۑ�w�@��c�搶�@���S���j�̊��܂ōl���ĉ��������̂ŁA���ψ���Ƃ��Ă͂��܂�����l���邱�Ƃ��Ȃ���������܂���B�������̋@����������āA�ȑO����C�ɂȂ��Ă����A���iWC�j���Ƃ̎Q���҂̃o���c�L�̌������ǂ��ɂ���̂���m�肽���ƍl���Ă��܂��B�n�̗������̐l�Ɋ��߂�ꂽ�Ƃ������ƂŎQ���҂������邱�Ƃ�����ł��傤���A�v���O���������ĎQ�����l������̂�������܂���B�Q���҂��������Ƃ����Ȃ炸�����ǂ��킯�ł͂���܂��A�Q���҂������Ƃ������Ƃ͑����̉���̊F�l�̃j�[�Y�ɉ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B����܂ł̗����ψ����^�c�ψ���ŁA���܂��܂ȃv���O�������l�����Ă��܂������A��������g�b�v�_�E���I�Ɍ��߂��A����̕��̂��ӌ����f���@��قƂ�ǂȂ������悤�Ɏv���܂��B�������A�u�����E��w����̃C�m�x�[�V�������S���w�ɗ^����C���p�N�g�v�Ƃ����w�p�V���|�W�E������悵�A����R���Q���ɖ{�w��Â̂��ƂŊJ�Â��܂����B�Óc����͂��ߗ�����܂߂�60���ȏ�̕����Q������܂����B�]���ɂ��A�N������WC�ȊO�̊��i���������̎��K���j������܂����B���̂悤�Ɋw����̒�ĂƂ��ĔN������WC�ȊO�̊����l�����܂��B��O��̑傫�Ȍ��т̂P�Ƃ��āA�{�w��z�[���y�[�W�̗����グ������܂����B�w��̎��s���ɂ�����g��^�c�ψ���̃��[�����O���X�g���������܂����B���݁A�u jabs.office[at]gmail.com ([at]->@) �v�Ƀ��[���𑗂�Ɗg��^�c�ψ���ɓ͂��܂��B��������Ƃ������łȂ��Ă��A�u���̂悤�Ȃ��Ƃ���������v�u���̐搶�̍u�����Ă݂����v�u����ȃV���|�W�E���͂ǂ����v�Ƃ������ӌ��E���v�]������A���Ђ��A���������B9. �z�[���y�[�W�f�ڏ��̂��m�点
�i�L��ψ���ψ����@����C��j
�Es���Ȋw�w��ł́A�֘A����w���V���|�W�E���̈ē��A������������̂��m�点�����z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���܂��B���e�̏������A�f�ڂ̂��₢���킹�͈ȉ��̒S���܂ł��肢���܂��Bmailto:public[at]jabs.jp ([at]->@)
�S���F�������g�E���������
10. �����ǂ���̂��肢
�i�����ǒ��@�c���F�K�j
�y���[���̂��肢�z�ߋ����[�����܂߂����N�x�̉��U���p�����G��52(2)�֓����������܂����B�w��̊����͉���̉��ɂ���Đ��藧���Ă���܂��B���[���̂������̕��́A���U������낵�����肢�\���グ�܂��B�U���p�������ꂽ����̕��͉��L�������������p���������B���͔N�z4,000�~�ł��B
�䂤�����s�U����
00170-5-297639
�����Z�@�ւ���̐U���p�����ԍ�
�Z���(�[���C�`�L���E)�X�i019�j���� 0297639
�y�w��ւ̓o�^��m�F�̂��肢�z
�`���́u�d�v�Ȃ��m�点�v�ɂ���܂��ʂ�A�����ǂɓo�^����Ă������̊F���܂̏����G��52(2)�ɓ��������Ă��������܂����B���ڒʂ��̏�A�ŐV�̏Z���A���[���A�h���X���������ǂɂ��o�^���������܂��悤���肢�������܂��B
�y�Z���E�������̕ύX�ɂ��āz
�Z���E��������ύX���ꂽ�ꍇ�́A���₩�Ɏ����ǂ܂ł��A�����������B�w��z�[���y�[�W���ɁA�o�^���ύX�E�މ�̂��߂̏�������������Ă��܂��B���A���̍ۂɁA�����p���������B
http://www.jabs.jp/application.html
�y���ݕs������̕��ɑ��邲�`���̂��肢�z
�u����̈ٓ��v�ɂ��L���܂������A���ݎ����ǂł́A���L����̕��ƘA�����Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��B���݂������m�̕������� ��܂�����A���L�̕����玖���Lj��ɏZ���E�����������A�����������悤�A���`�������肢�������܂��B
�i�h�̗��j�A���F�M�^���X�p���^���엺�^�F�䌒��Y�^��䖾�q�^�������^���R��F�^����a�Y
11. �_�E�����[�h
���ŐV�ł�Adobe Reader�ł������������B
��������������������������������������������������
���s�F���{�s���Ȋw�w��
��607-8175�@���s�s�R�ȋ���R�c��34
���s�k��w�D�S��E413�i�c���������j��
���{�s���Ȋw�w�����
jabs.office[at]gmail.com ([at]->@)
�ҏW�F�L��ψ���
��������������������������������������������������
| [�z�[��]�@[����ē�]�@ [�@�֎�]�@[�����]�@[�j���[�Y���^�[]�@[�֘A����Â�]�@[�j���[�X]�@[�w��g�D]�@[���₢���킹]�@[�����N]�@ Copyright(c)2008- Japanese Association of Behavioral Science. All Rights Reserved.�@ |